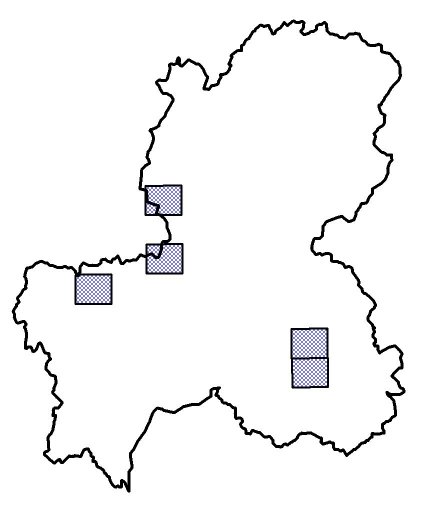| 形態の特徴 |
翅を広げた大きさ35mm前後の蝶。翅の色は表面は茶褐色、裏面は淡褐色で黒褐色の斑紋が並ぶ。雄の翅の表面は光の加減によって青色に輝く。 |
| 生息環境 |
丘陵帯から山地帯の草地に生息。クヌギやコナラなど落葉広葉樹がまばらにある明るい疎林や林縁部の草地に見られる。 |
| 生態 |
成虫は7月に出現する。夕方樹木の梢上を飛び回り昼間は草の上などで静止していることが多い。産卵は植物につくアブラムシ類の群れの中に行われ、幼虫はアブラムシの分泌物をなめて成長する。8月頃になるとクロオオアリにくわえられてアリの巣の中に入りアリから食物をもらって成長する。幼虫で越冬する。 |
| 分布状況 |
本州、四国、九州に分布。国外では朝鮮半島、中国に分布。県内では美濃地方の恵那市、蛭川村、高鷲村、坂内村、飛騨地方の朝日村などに確認記録がある。 |
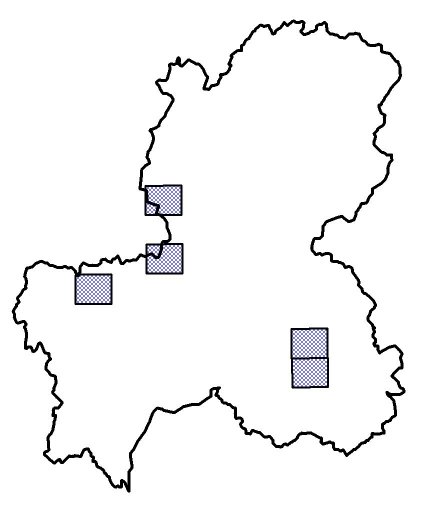
|
| 減少要因 |
生息環境となる二次草地の減少。生息環境はいわゆる"里山"と呼ばれる地域にあり、燃料材の供給源、茅場などとして定期的な草刈りにより維持されてきた二次草地である。しかし、こうした場所は生活様式の変化に伴いその価値がなくなって利用転換されたり、放置されて樹林化するなどして減少している。 |
| 保全対策 |
本種の生息環境となる二次草地は、そのまま手をつけずに保全するよりもむしろ草刈りなど積極的な環境管理が必要である。 |
| 特記事項 |
|